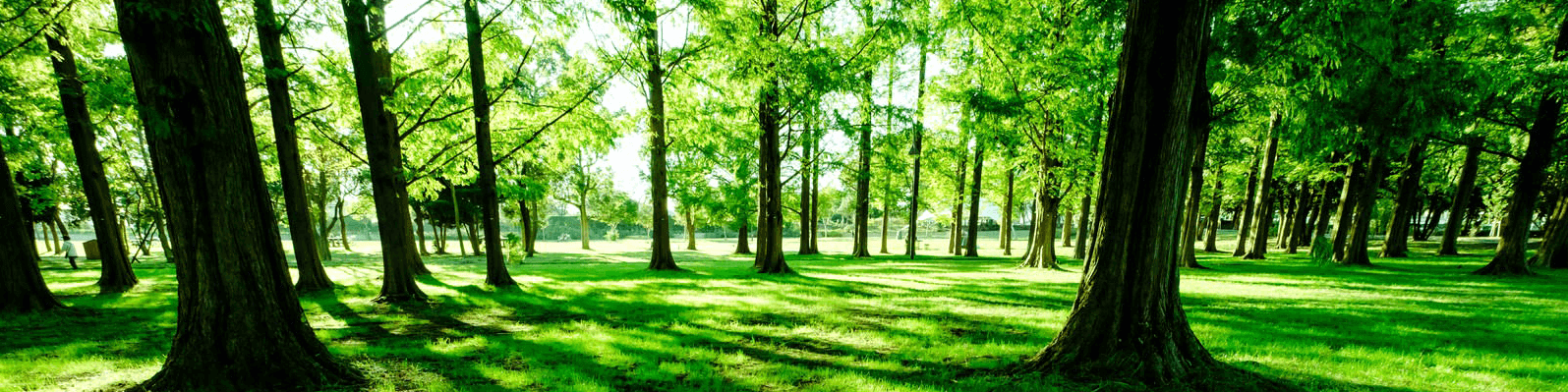デジタル時代の課題と新たな奉仕活動の可能性
デジタル化が急速に進展する現代社会において、若者へのデジタル教育はかつてないほど重要性を増しています。しかし日本では、スマートフォンの普及が進む一方で、パソコンやタブレットの所有率が低下する傾向にあります。調査によれば、子どもの約5割が学校以外で日常的にパソコンを使用していないという結果も出ています。AI(人工知能)などが経済成長を牽引するデジタル時代において、このままでは日本が世界に大きく後れを取る可能性が懸念されています。
こうした社会課題に対して、東京八王子ロータリークラブ(RC)が実施したプログラミングコンテストの事例は参考になります。特に、企業や地域との連携によって、ロータリーの奉仕活動がより大きな広がりと深いインパクトを生み出した過程は注目に値します。本記事では、この事例を通じて、企業連携による社会奉仕ムーブメントの可能性を探ります。
「デジタル先進都市」を目指す挑戦
東京八王子RCは、「八王子を日本一のデジタル先進都市に」という高い志を掲げ、地域を巻き込んだ活動としてプログラミングコンテスト(ブロコン)の開催に挑戦しました。これは単なるイベント開催ではなく、デジタル時代を担う若い世代への教育支援という社会奉仕の形を模索する挑戦でした。
コンテストに参加した子どもたちは、プログラミングを通じて人の意思を機械に伝え、ソフトウェアが多くのものを動かす現代の仕組みを肌で感じ取る様子が見られました。クラブ会員たちはこの姿を目の当たりにし、奉仕事業の可能性を強く実感したと言います。デジタル教育支援という形での社会貢献が、未来を担う子どもたちの成長に直接貢献できることが確認されたのです。
一歩踏み出したクラブ活動と見えてきた課題
第1回大会は学校の教室を借りての開催でした。限られた空間ではありましたが、子どもたちが考案した作品を生き生きと発表する姿に、クラブ会員たちは大きな感動を覚えたと伝えられています。しかし同時に、狭い教室では保護者の入場も制限されるなど、より大きなステージでの発表機会を作りたいという思いが強く湧き上がったようです。
また、このような小規模な形では活動自体も大きく育たないのではないか、という危機感も生じました。始まった活動をより大きく発展させ、より多くの子どもたちにプログラミングの楽しさを伝えるためには、新たな一歩を踏み出す必要があったのです。
ムーブメント創出に向けたビジョン
この初期の経験から、「ロータリークラブが地元企業の核となって新しいムーブメントを起こせないか」「デジタル時代のリーダーシップに貢献できないか」「地域全体を巻き込んだ活動のうねりをつくれないか」という思いが強くなったと報告されています。
クラブ単独での活動には限界があります。しかし、奉仕への高い志を持つロータリアンが核となり、地域の様々な力を結集すれば、より大きな社会的インパクトを生み出せるのではないか—そうした展望が見えてきたようです。地域を活性化させる一歩を踏み出したいという決意が固められました。
連携が生んだ新たな推進力
活動の拡大に向けて、東京八王子RCは重要な決断を下しました。それは実施組織の法人化です。こうして新たな組織として「一般社団法人 八王子デジタル教育支援協議会」(通称・ハチデジ)が設立されることになりました。
この発足会・設立総会には、文部科学省の課長や八王子商工会議所の会頭も出席し、八王子の未来を担うイベントとして注目を集めたことが報告されています。市内大手企業も参画するなど、ロータリー以外の力も結集し始めました。単なるロータリークラブの活動から、地域全体の取り組みへと発展する基盤が整ったのです。
設立にあたっては、会費や寄付・協賛金を合わせて約400万円が集められました。理事や幹事にはクラブ会員が名を連ね、新たに事務局も設置されました。また、商工会議所には協力が仰がれました。これらの取り組みには、クラブ単独開催の限界を突破したいという強い思いが込められていたと考えられます。
企業や公的機関との連携は、活動の幅を広げるだけでなく、様々な知見や資源の共有を可能にします。特に以下の関係機関との連携強化が進められました:
- 市との連携(市長との意見調整、協力体制強化)
- 地域のIT企業・団体との連携
- 文部科学省との連携(講師要請、教育施策との整合性調整)
これらの課題に対して、幸いにも各関係機関との協力体制が徐々に強化されていきました。
広がる活動と深まるインパクト
ハチデジの設立は、新生プログラミングコンテスト大会を成功に導くきっかけとなりました。応募数、会場規模ともに大きく飛躍した第3回大会を経て、第4回大会を迎える頃には全国有数の規模に成長しました。
また、活動の幅も広がりました。学生を対象としたDXコンテストも開催され、学生から提供されたDX化のアイデアが将来的に採用につながるというメリットも生まれました。さらに、「サポート家族会員」制度も導入され、より多くの人々が活動に参加できる仕組みが整いました。
このように、当初は一つのロータリークラブによる小規模な取り組みだったプログラミングコンテストが、企業や地域との連携によって大きなムーブメントへと発展したのです。子どもたちや学生に対して、単なる体験の機会だけでなく、将来につながるキャリアの可能性まで提供できるようになりました。
協働から生まれる社会貢献の新たな形
東京八王子RCの事例は、ロータリークラブのイニシアチブが、企業や地域の力を巻き込むことでどのように可能性を広げられるかを示しています。「夢を大きく描き、小さな一歩を踏み出す」—このシンプルながら力強い教訓が、活動の原動力となったと考えられます。
ロータリークラブは、その地域の職業人の集まりであり、様々な企業や団体とのネットワークを持っています。この強みを活かし、社会課題の解決に向けた協働の場を作り出すことができるのです。企業連携による奉仕活動は、単独では成し得ない大きなインパクトを生み出す可能性を秘めています。
企業連携による社会奉仕ムーブメントの展望
東京八王子RCの事例が示すように、企業・地域連携による社会奉仕ムーブメントは、より広範で持続的なインパクトを生み出すことができます。ロータリークラブがその触媒となり、地域の様々なステークホルダーを巻き込むことで、当初の想像を超える成果につながる可能性があるでしょう。
デジタル教育支援、環境保全、貧困対策、災害支援など、様々な社会課題に対して、ロータリークラブは企業や地域との連携を通じて、新たな解決策を見出していく道筋を示しています。そして、その先には社会奉仕の理念がより広く社会に浸透した世界が待っているのかもしれません。
地域の課題に向き合い、解決を目指すとき、一人の力は小さくとも、様々な力が結集することで大きなうねりとなります。各地域でも、企業や団体との連携による社会奉仕の新たな形を模索する価値があるでしょう。小さな一歩から、大きなムーブメントが生まれる可能性があります。