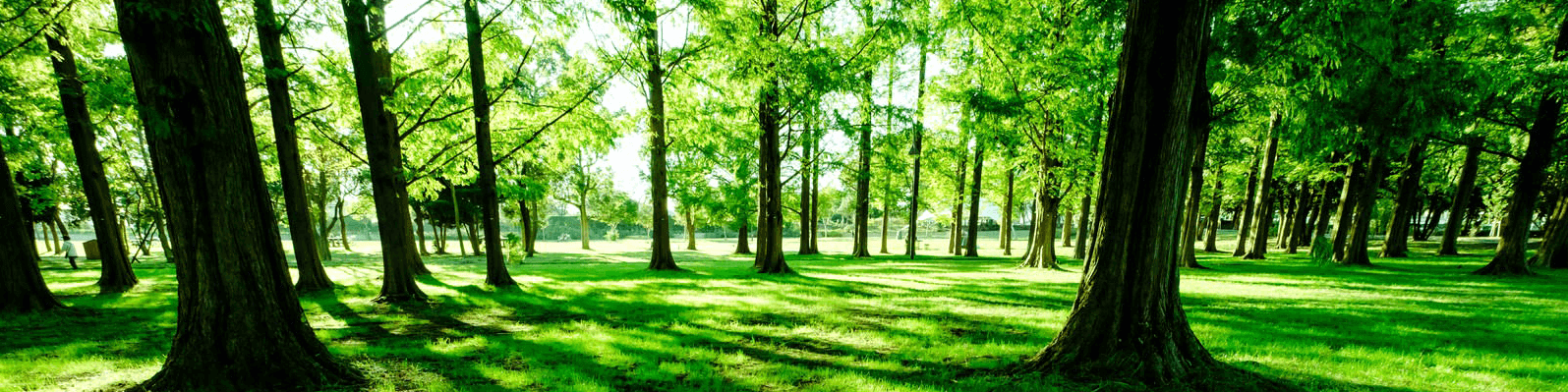私たちロータリアンの多くは、企業経営や国際ビジネスに携わっています。この度、国際政治学者の高橋和夫氏による講演から、ドナルド・トランプ氏の再選がもたらす影響について、重要な示唆を得ることができました。
メディアでは「異常な人物」として描かれがちなトランプ氏ですが、高橋氏は250年のアメリカ史を振り返ると、彼の戦略は実は「多数派」の意見に忠実であり、決して異常なものではないと指摘されています。むしろ、これまでの大統領が例外的な存在だったとも言えるのです。
トランプ勝利の背景:激戦州の攻防と隠れた票田の重要性
2024年の大統領選挙において、トランプ氏の勝利を決定づけたのは、ペンシルベニア州での「神様がついている」と思わせるような一連の出来事でした。世論調査では共和党と民主党が互角とされていましたが、最終的にトランプ氏が圧勝する結果となりました。
この勝利の鍵となったのは、アメリカの「勝者総取り方式」の選挙人制度における激戦州の獲得です。ウィスコンシン州、ミシガン州、ペンシルベニア州、ジョージア州、ノースカロライナ州、アリゾナ州、ネバダ州という7つの激戦州を、トランプ氏は全て制しました。
特に注目すべきは、デトロイトを擁するミシガン州の動向でした。この州には、アメリカ全体の約1%に対して約3%という高い割合で中東系移民やイスラム教徒が居住しています。選挙キャンペーンと同時期に進行していたイスラエルによるガザ侵攻により、中東にルーツを持つ有権者たちは、イスラエルへの武器供与を続けるバイデン政権に強い怒りを覚えていました。
一方で、トランプ氏も過去にイスラム教徒の入国禁止措置を実施した経緯があり、彼らは板挟みの状況に置かれていました。しかし、トランプ氏は「俺は平和の候補。戦争を止めるから」というメッセージを前面に打ち出し、結果的にミシガン州で約8万票差での勝利を収めました。全米のイスラム教徒の票においても、前回選挙の7%から20%超へと3倍以上に支持を拡大し、政治的な「復活」を果たしたのです。
「アメリカ・ファースト」の歴史的系譜:孤立主義は米国の伝統か
「アメリカ・ファースト」というスローガンは、トランプ氏の独創ではありません。高橋氏によれば、トランプ氏はこの思想を掲げた「3人目」に位置付けられます。
初代は、建国の父ジョージ・ワシントン(1789-1797年)でした。彼は、ヨーロッパの永続的な同盟に加わらないよう警告しました。当時のアメリカは弱小国であり、ヨーロッパ諸国が分裂して互いに争うことで、アメリカが国内の発展に専念できるという戦略的な判断がありました。
2人目はパット・ブキャナンで、1990年代の湾岸戦争時に国際機関への資金供与や外国からの関税に批判的な立場を取り、国内産業の保護を主張しました。同時期にロス・ペローも1992年の大統領選でNAFTAに反対し、「メキシコがアメリカの雇用を吸い取る音が聞こえる」と訴え、後のトランプ支持者層の形成に寄与しました。
また、チャールズ・リンドバーグは第二次世界大戦中、「アメリカ・ファースト委員会」を率いて参戦に反対しました。国民的英雄だった彼は、ルーズベルト大統領の英国支援政策に強く抵抗しましたが、日本の真珠湾攻撃によってアメリカは参戦を余儀なくされました。
アメリカの第一次・第二次世界大戦への介入も、実はドイツのヨーロッパ統一を阻止し、国内に強大な軍事体制を持つ必要を避けるという「伝統」に根差していました。冷戦終結後、アメリカは「軍事力(Military)」「資金力(Money)」「メディア(Media)」「メッセージ(Message/ソフトパワー)」「人材(Manpower/移民)」という「5つのM」からなる圧倒的な国力を獲得し、世界への介入主義と国内重視の孤立主義の間で揺れ動いてきました。
しかし、2001年の9.11同時多発テロがこの議論に終止符を打ち、アフガニスタンやイラクでの「終わりのない戦争」へと突入しました。国民の「もう戦争は勘弁してくれ」という疲弊感が、2016年にイラク戦争を「ばかげた戦争」と批判したトランプ氏の勝利へと繋がったのです。
トランプ政権の人事戦略:ビジネス界と家族の繋がりが動かす政策
高橋氏は、トランプ政権において「人事が万事」であり、「家族経営」のような特徴があると分析しています。彼の周囲に集まるのは、選挙資金を提供した者、票を集めた者、あるいは親戚や旧友といった顔ぶれです。
国防次官のエルブリッジ・A・コルビーは、中国を主要な敵と見なし、アメリカは世界中で戦争する力はないと主張し、ウクライナ支援にも反対の立場を取っています。
イーロン・マスクは、常にトランプ氏の傍らにいる存在として、移民政策に大きな影響を与えました。マスク氏が「移民のエンジニアがいなければアメリカのハイテク企業は回らない」と進言したことで、トランプ氏は優秀な外国人材のビザ発給を支持するようになりました。
アラブ・中東担当の特別顧問マサド・ブーロスは、トランプ氏の末娘の夫の父親であり、レバノン系実業家としてミシガン州のイスラム教徒やアラブ系住民への働きかけで票獲得に貢献しました。
中東特使のスティーブ・ウィトコフは、不動産業界でのトランプ氏の古くからの友人で、ユダヤ系富豪からの資金集めに尽力し、ガザの一時停戦実現にも関与しています。
このように、トランプ政権の政策は、選挙協力者や親族の利害が強く反映される傾向にあります。公約では中国への対応とイスラエル支持が重視されますが、これらも「アメリカ・ファースト」、つまり国民の「もう戦争はいい」という声に応えるという視点から判断されることになります。
グローバルビジネスへの示唆:米中「新冷戦」の特異性と地政学リスク
高橋氏は、現在の米中関係を「新冷戦」と呼ぶことには注意が必要だと指摘しています。過去の米ソ冷戦とは異なり、現在の米中経済は「一体化」しており、非常に密接な関係にあります。例えば、アメリカ製のスマートフォンも内部には中国の部品が多く使われているという現実があります。
トランプ氏は「私は平和の大統領だ」と訴え、ウクライナ戦争もガザ戦争も止めることを公約しています。特に「アーリントン墓地にこれ以上のお墓を増やさない」という約束は、国民の戦争疲弊に応えるものです。
私たちロータリアンの多くが携わる国際ビジネスにおいて、このような国際政治の動向がサプライチェーンや市場戦略に直接影響を与える可能性を深く理解する必要があります。地政学的なリスクがビジネスに与える影響は計り知れず、既存の枠にとらわれない柔軟な事業運営がこれまで以上に重要となるでしょう。
変化の時代に経営者が持つべき視点
国際政治学者の分析から見えてくるのは、トランプ氏の戦略が、表層的なメディア報道だけでは捉えきれない、アメリカの歴史的深層と国民感情に根差しているという事実です。
私たちロータリアンとして、そしてグローバルビジネスの経営者として、こうした複雑な国際情勢を理解し、単なる政治的レトリックではなく、その裏にある民意や構造的変化を読み解く能力が不可欠です。不確実性の高い時代において、地政学リスクをビジネス戦略に組み込み、変化に適応する柔軟な思考が、企業の持続的な成長を左右する鍵となるでしょう。
ロータリーの理念である「職業奉仕」を実践する上でも、国際情勢への深い理解は、より良い経営判断と社会貢献につながるはずです。