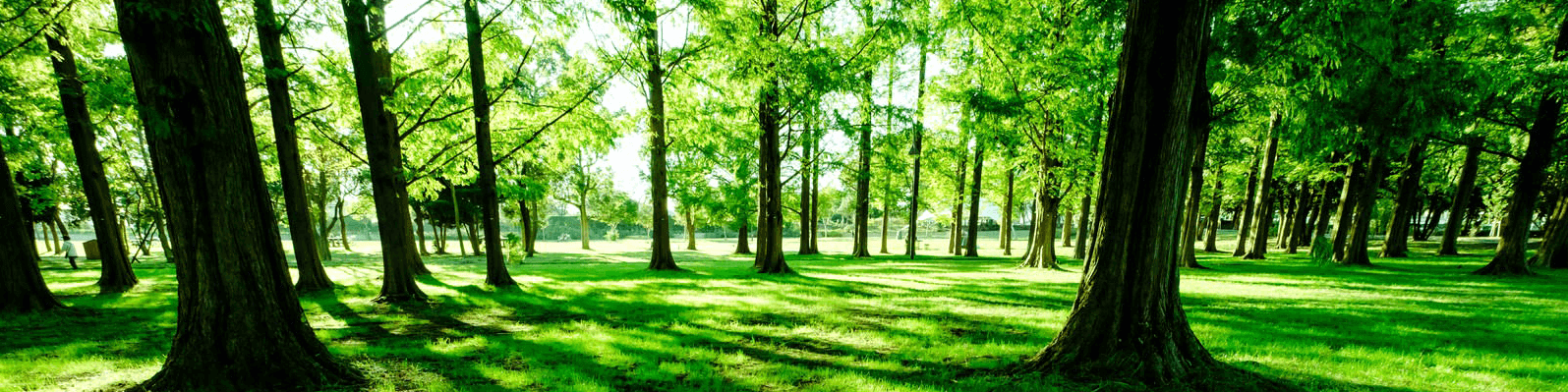今日のグローバルビジネスにおいて、企業の社会的責任(CSR)や環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みは、大きな転換期を迎えています。かつて「義務」として捉えられていた社会貢献活動が、今や企業の持続的成長を左右する重要な「戦略」へと変化しているのです。私たちロータリークラブは、100年以上にわたる活動を通じて、この転換を先駆的に実践してきました。本稿では、私たちの経験から得られた知見を基に、社会貢献を成長戦略として位置付けることの意義を考察します。
従来の「義務」的アプローチの限界
日本社会において、社会貢献活動はしばしば「義務」として捉えられてきました。私たちロータリーの活動においても、この傾向は顕著に見られます。例えば、地区大会への参加を「出席義務」として捉える会員が多く、これが会員減少や高齢化という課題の一因となっています。
「義務」として行動するパターンは、日本社会特有の現象です。この受動的な姿勢は、活動への情熱を損ない、会員間の絆を弱め、組織全体の活力を奪う結果を招いています。義務感から参加する活動では、本来得られるはずの学びや成長の機会を逃し、組織の魅力も半減してしまうのです。
「権利」への転換~主体的参加がもたらす変化~
ある会員は、地区大会への参加を「権利」と主張しています。なぜなら、そこではロバート・キャンベル氏や福岡伸一氏のような著名人の貴重な講演、将来母国で要職に就く可能性のある米山奨学生による深い洞察、質の高い文化的プログラムなど、他では得難い機会が提供されるからです。これらを享受しないのは、自らの「権利」を放棄しているに等しいという考え方です。
米国市民が陪審員としての役割を「当然の権利」と捉えるように、社会貢献活動を「権利」として認識することで、参加者の意識は劇的に変化します。主体的な参加は、個人の成長機会を最大化し、組織への貢献意欲を高め、活動の質を向上させる好循環を生み出します。
「成長戦略」としての社会貢献
社会貢献を「成長戦略」として位置付けることの本質は、以下の3つのメカニズムにあります。
第一に、イノベーションの創出です。私たちロータリーは、従来の枠にとらわれない多様なクラブ形態を柔軟に設定できるようになりました。韓国では衛星クラブの拡大により約1,000人の新会員が誕生し、東南アジア、アフリカ、ヨーロッパでは特定の課題に取り組む「分野特化型クラブ」が繁栄しています。社会課題への取り組みが、組織形態や運営方法のイノベーションを促進しているのです。
第二に、人材の成長と獲得です。ロータリー・インターナショナルの「行動計画」では、「参加者基盤の拡大」と「積極的参加の促進」を優先事項に掲げています。新会員は新たな発想とエネルギーをもたらし、既存会員も多様な奉仕活動を通じて専門性を高め、リーダーシップを発揮する機会を得ています。社会貢献活動が、優秀な人材を引き付け、育成する強力な磁場となっているのです。
第三に、ネットワークの拡大です。私たちは「意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと」を目的とし、世界的なネットワークを構築してきました。2025年のカルガリー国際大会には140カ国から1万6,000人超が集まり、ビル・ゲイツ氏とのパートナーシップによりポリオ根絶のために今後3年間で最大4億5,000万ドルの支援が決定されました。このようなグローバルな連携は、組織の影響力を飛躍的に拡大させています。
実践事例
私たちの活動の中から、成長戦略として特に成功している事例を紹介します。
ロータリー米山記念奨学事業は、「人づくり」を目的とした日本独自の最大規模の民間奨学金事業です。2025学年度には964人、これまで延べ2万4,830人の留学生を支援してきました。この事業は単なる経済支援ではなく、世話クラブの会員がカウンセラーとなることで、国際的な人的ネットワークを構築し、会員企業のグローバル展開にも寄与しています。
2720 Japan O.K.ロータリーEクラブは、オンラインの特性を活かしつつ対面交流も重視し、創立から着実に会員数を増やしています。フィリピンへのミシン寄贈による縫製技術支援、インターアクトクラブの提唱、U-30会員制度構想など、従来の枠を超えた活動により、若い世代の参画を実現しています。
これらの事例に共通するのは、社会貢献活動が組織の成長エンジンとして機能している点です。活動を通じて得られる学び、人脈、評価が、組織と個人の両方に具体的な価値をもたらしています。
企業のCSR/ESGへの応用
私たちロータリーの経験は、企業経営者にとって重要な示唆を含んでいます。
まず、社会貢献活動を「コスト」ではなく「投資」として捉え直すことです。私たちが実践してきたように、適切に設計された社会貢献活動は、イノベーション創出、人材育成、ネットワーク構築という具体的なリターンをもたらします。
次に、従業員の主体的参加を促す仕組みづくりです。活動を「義務」ではなく「機会」として位置付け、参加者が成長と達成感を得られる設計が重要です。私たちの「四つのテスト」のような明確な価値基準を設定し、活動の意義を組織全体で共有することも効果的です。
最後に、長期的視点での価値創造です。ロータリー財団が「無限の機会への扉」と位置付けられているように、CSR/ESG活動は短期的な成果だけでなく、組織の持続的発展の基盤となります。私たちのクラブを「次の世代に託す贈り物」と捉えるように、企業の社会貢献活動も未来への投資として設計すべきです。
変化の時代における新たな経営パラダイム
私たちロータリーの実践は、社会貢献が組織の持続的成長を実現する強力な戦略となることを証明しています。「義務」から「権利」へ、そして「成長戦略」へという転換は、単なる意識の変化ではなく、組織運営の根本的なパラダイムシフトを意味します。
不確実性が高まる現代において、社会との共生なくして企業の持続的発展はありえません。私たちロータリーが示してきた道筋は、企業経営者にとって、CSR/ESGを真の競争優位の源泉として活用するための実践的な指針となるでしょう。社会貢献を成長戦略の中核に据えることで、企業は社会的価値と経済的価値の両立を実現し、真に持続可能な発展への道を歩むことができるのです。