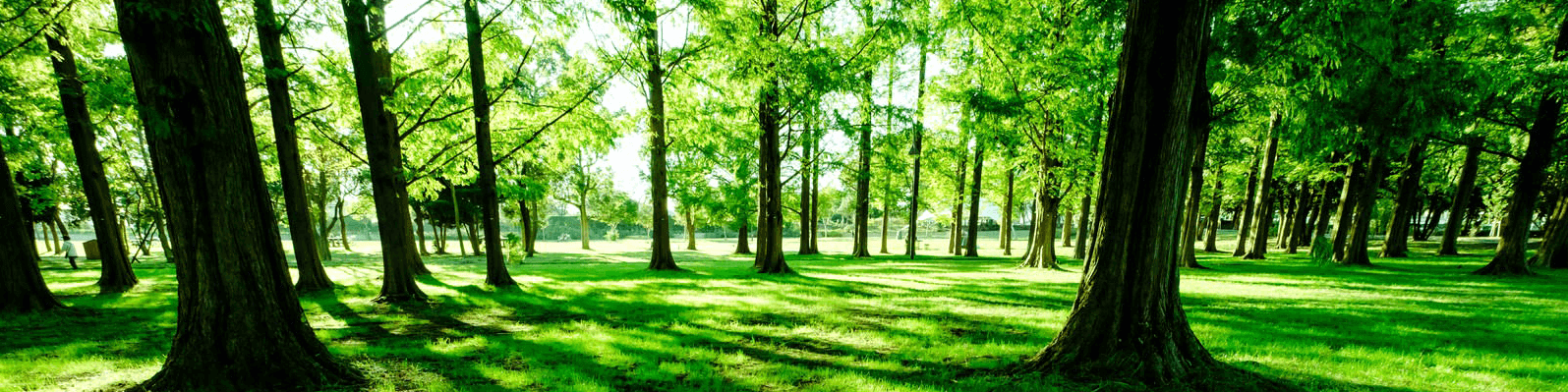通過駅のハンディキャップを戦略に変える
企業が全国展開を目指す中で、あえて地域に根差した「ローカルブランド」としての地位を確立し、成功を収めた企業があります。その企業とは、崎陽軒です。
本稿では、横浜名物崎陽軒の発展の歴史を紐解き、 「通過駅」という経営上のハンディキャップをいかにして差別化のバネにしたか、そして地域ブランドを確立するための具体的な戦略について考察します。
崎陽軒の創業と「ローカルブランド」の必要性
崎陽軒は1908年(明治41年)に横浜駅構内売店として開業しました。初代社長の野並茂吉氏(栃木県鹿沼市出身)は、幾多の苦難を経て横浜にたどり着き、駅弁販売に携わることになります。
しかし、当時の横浜駅は駅弁販売にとって不利な 「通過駅」 でした。乗客は始発駅である東京駅で弁当を購入済みであったり、大阪方面からの乗客は東京駅到着を目前に控えており、新たに弁当を買おうという気にならなかったため、売上が伸び悩んでいました。
茂吉社長は、小田原のかまぼこや浜松のうなぎといった各地の駅で名産品が売れていることに着目し、横浜の名産品を駅で販売しようと考えました。しかし、横浜は歴史が浅い開港地であり、城や独自の食文化がない「ひなびた漁村」にすぎず、名産品が存在しませんでした。
そこで茂吉氏は、「ないのなら作ってしまおう」と決意し、横浜の中華街で提供されていた「シウマイ」に着目しました。この発想の転換が、後の崎陽軒の成功の基盤となります。
製品の「冷めても美味しい」差別化戦略
シウマイは、本来温かいうちに食べるのが美味しい料理であり、冷めると豚肉の独特な臭みが出て美味しくなくなります。列車内で客が食べる頃には冷めてしまうため、崎陽軒は 「冷めても美味しいシウマイ」 を開発する必要がありました。
茂吉氏は中華街から点心職人呉遇孫氏を招き研究を重ね、豚肉に干し帆立貝の貝柱を混ぜることで、冷めても美味しく作れるシウマイを開発しました。これは、互いに異なる場所で育った豚肉と帆立貝が一つになり、お互いの味を引き立て合うという製品の差別化となりました。
また、ガタガタ揺れる列車内でテーブルなしで食べられるよう、楊枝で刺して一口で食べられる小粒にした点も工夫の一つです。このサイズは販売開始当時(1928年)から変わっていません。利用シーンを徹底的に想定した商品開発が、競合との明確な差別化を生み出しました。
さらに、後に発売された「シウマイ弁当」(1954年)のご飯についても、単なる炊飯ではなく、おこわの炊き方と同様に地下ボイラーの熱い蒸気で高圧で蒸す 「蒸気炊飯方式」 を採用しました。これは、茂吉氏が「お焦げができない炊き方」を追求した結果であり、「冷めても美味しい」もちもち感のあるご飯を実現しています。
このように、崎陽軒は単に地域の食材を使うだけでなく、駅弁という販売形態に最適化された製品開発を徹底することで、他社には真似できない独自のポジションを確立しました。
話題性のある販売促進と組織の士気向上
戦後、崎陽軒のシウマイ販売を大きく伸ばした要因が、1950年(昭和25年)に登場した女性販売員 「シウマイ娘」 でした。荒廃した銀座の街角で、タバコのキャンペーンをしていた女性販売員の姿から着想を得て、女性販売員を駅のホームに登場させました。
当時の列車は停車時間が長く、乗客は窓から顔を出して弁当を購入していました。シウマイ娘は「愛らしい若い女性」という話題性で注目を集め、評判となり、ついには人気作家・獅子文六の小説『やっさもっさ』にも登場し、映画化されました。これにより、「横浜にはシウマイ娘がいて、崎陽軒のシウマイを売っている」と全国的に広まり、大きなPR効果を生みました。
この事例は、製品の品質だけでなく、販売方法や顧客接点の工夫が地域ブランドの認知度向上に大きく貢献することを示しています。
また、1991年の湾岸戦争がきっかけで始めた工場見学ツアーは、従業員のモチベーションを劇的に向上させました。当初、「見せ物ではない」と従業員から反対があったものの、見学者が次々と訪れることで、従業員は「自分たちの仕事が多く関心を持たれている」と実感するようになりました。
工場のような接客がない現場部門の従業員に、自らの仕事の社会的な評価を実感させる機会を提供することは、士気向上につながる教訓となりました。この工場見学ツアーは、日本経済新聞の「何でもランキング」で大手企業が並ぶ中で第9位に食い込み、社会貢献にもなっています。
ローカルブランド経営理念と六ヶ条
崎陽軒は創業100周年(2008年)を機に、新たな経営理念の一つとして、「崎陽軒はナショナルブランドをめざしません。真に優れた『ローカルブランド』をめざします」と定めました。
この理念は、2代目社長が抱いた疑問に対し、日本青年会議所時代に大分県の平松守彦知事(当時)の 「真にローカルなものこそ、インターナショナルなものになり得る」 という言葉に触れたことが根底にあります。アルゼンチンタンゴのように、特定の地域に深く根差した文化こそが、国際的な価値を持ち得るという視点です。崎陽軒はあくまで横浜のローカルブランドとして歩むことを決定しました。
地域ブランドが成功するための共通項として、「地域ブランドの6ヶ条」が紹介されています。
- 地域の誇りである
- 地域限定である
- 地域の文化、風土と一体になっている
- 安心安全が見えるように分かるようにしている
- 地域の価値を引き立てるもの
- 地域の人たちが日常的に消費している (最も重要)
地域の人たちが日常的に消費しているからこそ、その地域外の人々も「地元が認めているのだから安心だ」と感じるため、地元住民の応援と消費が非常に重要視されています。観光客向けの商品開発に偏ることなく、地元住民に愛される製品であり続けることが、地域ブランドの本質であるといえます。
この6ヶ条は、単なる理念ではなく、地域ブランドを構築する際の具体的な指針として機能します。特に第6条の「地域の人たちが日常的に消費している」という要素は、ブランドの信頼性と持続可能性を担保する最も重要な基盤となります。
地域密着型戦略の現代的意義
崎陽軒の事例が示すように、地域ブランドの差別化戦略は、地理的な制約や歴史の欠如といったハンディキャップを逆手にとり、「冷めても美味しい」という独自の価値創造に昇華させる点にあります。
通過駅という不利な条件を克服するために、横浜独自の名物を創出し、製品特性を徹底的に追求し、話題性のある販売促進を展開し、最終的にはローカルブランドとしての地位を確立するという一連の戦略は、現代の企業経営にも多くの示唆を与えます。
特に注目すべきは、全国展開を目指さず、あえて地域に根差すことを選択した経営判断です。グローバル化が進む現代においても、地域の文化や風土と深く結びついた価値提供は、大手企業との差別化において有効な戦略となり得ます。
また、工場見学ツアーのように、従業員の士気向上と社会貢献を両立させる取り組みは、企業の社会的価値を高めるCSV(Creating Shared Value)の考え方にも通じます。地域住民との関係性を深め、従業員が誇りを持って働ける環境を整えることで、持続可能な経営基盤を構築できます。
崎陽軒の成功は、単なる商品開発の工夫だけでなく、地域との関係性、従業員の意識、経営理念の一貫性が相互に作用した結果です。地域ブランドを目指す企業は、これらの要素を総合的に捉え、長期的な視点で戦略を構築することが求められます。