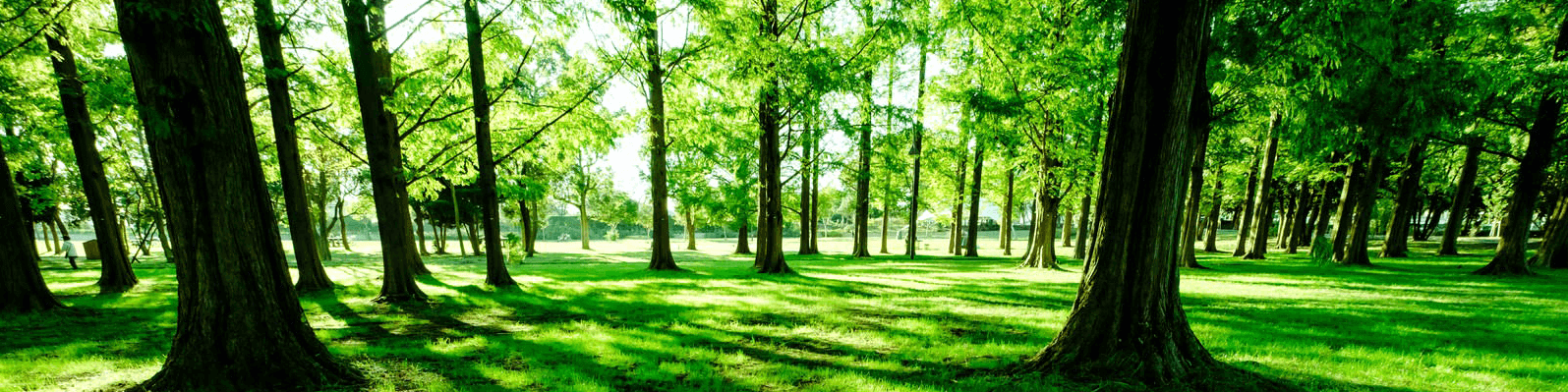CSV(共有価値の創造)と地域社会の経済発展
現代の企業経営において、社会的な課題解決と経済的な価値創出を両立させるCSV(Creating Shared Value:共有価値の創造)の重要性が高まっています。本記事では、特に地域に根差した日本の蔵元ロータリアンたちが、酒造りという職業奉仕を通じて、いかに地域の歴史、文化、環境、そして人々の生活に深く関わり、CSVを実践しているのか、具体的な事例を通じて検証します。
文化・伝統の継承と地域アイデンティティの強化
日本酒、焼酎、泡盛は、ユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒造り」の技術に支えられており、地域の風土と文化を映し出し、人々のつながりを育んできました。この伝統を守り、地域文化を発信することが、結果的にビジネスの機会を生んでいます。
歴史的な酒蔵の再興
埼玉県川越市は「蔵の街」として知られますが、2000年に最後の酒蔵が廃業していました。これを受け、実家が酒蔵を営んでいた川越RC会員が行政や市民の熱意を背景に2007年に小江戸鏡山酒造を設立し、歴史ある地酒「鏡山」の復刻に取り組みました。
さらに、埼玉唯一の酒造好適米「さけ武蔵」の生産組合立ち上げに参加し、地域の農家と協力することで、地元の文化を象徴する「蔵の街唯一の酒蔵」としての役割を果たし、地域文化の発信源となっています。
地域観光と愛着の創出
佐賀県鹿島市は人口約2万8,000人の小さな町ですが、江戸時代から酒造りが盛んで、現在も5軒の醸造元があります。鹿島RC会員らが中心となり、2011年に「鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会」を発足しました。「酒蔵を巡り、蔵人と触れ合い、酒を味わう」というコンセプトの旅のスタイルを提案し、官民一体で推進しました。
その結果、初回のイベントで3万人、近年は約10万人もの来訪者を集め、市内のあらゆる産業に多大な経済効果をもたらしました。この活動は、地元住民が「鹿島には酒蔵ツーリズムもある」と再認識するきっかけとなり、地元への愛着をさらに強める要因にもなっています。
複合的な社会課題解決(環境・福祉・教育)
ロータリークラブ会員の蔵元は、製品の製造過程や原材料を通じて、複数の地域課題を同時に解決し、持続可能な社会価値を創造しています。
環境保全と福祉・地域産業の活性化
滋賀県の八日市南RC会員の蔵元は、琵琶湖の飛び地である「権座」の町づくり事業(権座プロジェクト)に2008年から参画しています。この取り組みは、次のような多面的な価値を創造しています。
伝統と環境の保護
復活した幻の酒米「滋賀渡船6号」を使用し、伝統的な農耕文化と豊かな水辺生態系を守る滋賀の原風景を守ることに貢献しています。
地域産業・福祉との連携
ラベルに琵琶湖の生態系保全とヨシ産業活性化につながるヨシを混ぜた和紙を使用し、さらにそのラベル作りを福祉施設に依頼して障害者の就労支援を行っています。
資源の循環利用
精米時に出る米ぬかを地元集落営農組合や授産施設、飲食店などの協力を得て、地域内で美味しく再利用するための研究開発を実施しています。
震災復興とキャリア教育への進化
山口県の蔵元は、東日本大震災以降、風評被害払拭を兼ねた農業復興事業として「福島×銀座×山口 酒づくりプロジェクト」を立ち上げました。福島産の酒米を使って酒を製造・販売し、福島の農業復興支援を10年間にわたり継続しています。
さらにこの取り組みは、福島市立西信中学校の地域連携型キャリア教育「酒米作りで6次化を学ぶ」という授業へと進化しています。中学生が田植えや稲刈りを体験し、蔵元会員や販売担当の会員が、生産(1次産業)、製造(2次産業)、販売(3次産業)を通じた産業の6次化について講演しています。
CSRからCSVへの視点の移行
私たち会員企業は、持続可能な発展を目指す上で、従来のCSR(企業の社会的責任)を超えて、CSV(共有価値の創造)へと視点を移行させていることを提案しています。
自然環境の保護と次世代への継承
新潟県の朝日酒造(新潟南RC・長岡東RC会員)は、創業以来、豊かな自然環境に支えられて酒造りを続けてきました。同社は、CSRという概念が広がる以前の40年以上前から、自然環境の指標昆虫であるホタルの保護活動を地域住民と共に実施しています。
この活動は、単なる環境保護に留まらず、地元の小学校でホタルに関する授業を行うなど、「おいしいお米、おいしいお酒を育む自然環境を守り、次世代につないでいく」という企業の継続的な使命を、教育活動を通じて実現しています。これは、事業の持続性(酒造り)と、地域社会の価値(環境と教育)を同時に高めるCSVの取り組みとして位置づけられています。
持続可能な地域経済発展と私たちロータリーの役割
会員蔵元のこれらの活動は、地域社会の文化や自然環境といった「地域固有の資産」を最大限に活用し、それを社会貢献と結びつけることで、単なる利益追求ではない、持続可能で価値の高いビジネスモデルを構築していることを示しています。
これらの活動が、地域社会の信頼と誇りを高めつつ、経済を活性化させるためのモデルケースとなることを願います。