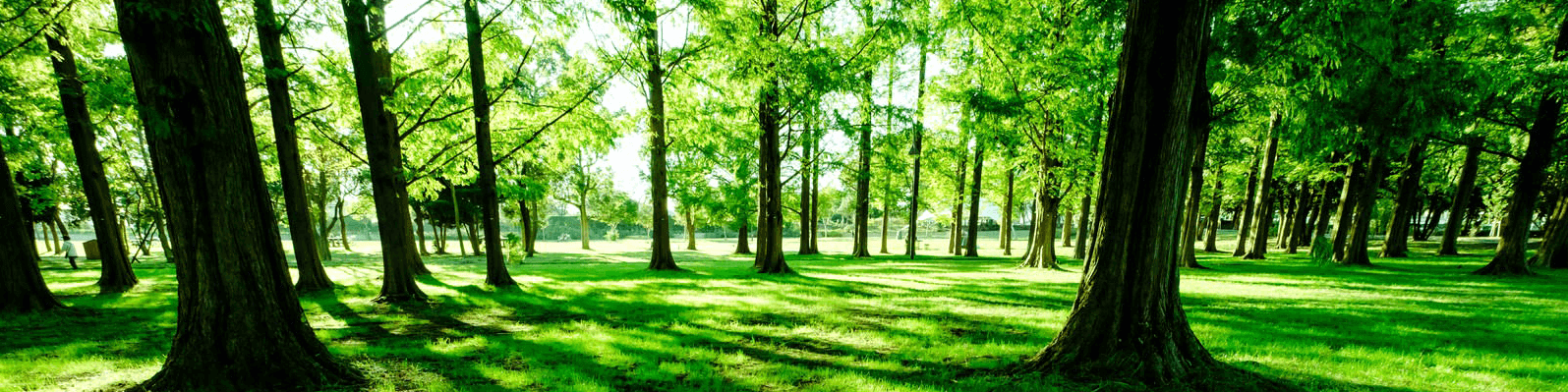心響学 主宰 / 一般社団法人 心呼吸の方法 代表理事 の石田 由美子様に寄稿いただきました。
30年間続く社会課題
厚生労働省が公表している「学歴別就職後3年以内離職率の推移」のデータを見ると、ある事実が浮かび上がります。大卒の新卒者における3年以内離職率は、昭和62年(1987年)から令和5年(2023年)まで、約30年以上にわたって概ね3割前後で推移し続けているのです。
平成7年(1995年)の32.0%から令和5年(2023年)の34.9%まで、数ポイントの変動はあるものの、根本的な改善は見られません。つまり、10人採用すれば3人が3年以内に離職するという構造が、30年以上も固定化されているのです。
この数字の背後には、キャリアの出発点でつまずく若者たち、そして採用活動に多大な投資をしながら人材を失う企業の姿があります。
参考資料: 厚生労働省「学歴別就職後3年以内離職率の推移」
採用コストから見る経済的損失の実態
企業が新卒採用にかける予算は決して小さくありません。マイナビの2024年卒企業新卒内定状況調査によれば、採用全体にかかる費用の1社あたり平均は約287万円です。上場企業では約917.6万円、非上場企業でも約233.1万円に上ります。
これを入社予定者1人あたりの採用費に換算すると、全体平均で約56.8万円となります。上場企業では約49万円、非上場企業では約57.5万円です。
ここで3年以内離職率3割という数字を掛け合わせると、深刻な問題が見えてきます。仮に10人を採用した場合、採用コストは568万円。そのうち3人が離職すれば、約170万円の採用費用が無駄になる計算です。
しかも、この金額は採用にかかった直接的なコストのみです。実際には、入社後の研修費用、教育コスト、そして離職による業務への影響など、間接的な損失も加わります。一人あたり50万円以上の採用費用が、3人に1人という高い確率で失われ続けています。
これは個別企業の問題に留まりません。日本全体で見れば、膨大な経済的損失が毎年繰り返されている社会課題なのです。
参考資料: マイナビ「新卒採用の予算について」(2024年卒企業新卒内定状況調査)
ミスマッチはなぜ生まれるのか
30年間も変わらないこの離職率の高さは、企業が求める人材と就職希望者の企業像のミスマッチが根本原因だと私は考えています。
なぜミスマッチが起きるのでしょうか。その背景には、求職者側の就活テクニック偏重があります。
「どのようにすれば企業に好印象を持ってもらえるのか」「面接でどう答えれば評価されるのか」。多くの就職活動は、こうした「どう見られるか」を優先する姿勢に支配されています。就活マニュアルは溢れ、面接対策講座は盛況です。模範解答を覚え、企業が求める人物像に自分を当てはめようとします。
しかし、テクニックで入社できたとしても、本来の自分の個性と企業文化が合わなければ、やがて違和感は大きくなります。「こんなはずではなかった」という思いは、離職という選択につながっていきます。これは極めて自然な帰結です。
表面的なテクニックで取り繕った就活は、企業にとっても求職者にとっても不幸な結果をもたらします。企業は自社に本当に合う人材を見極められず、求職者は自分に本当に合う職場を見つけられません。こうして30年間、同じ構造が再生産され続けているのです。
本来の自分を知ることから始める就活支援
私はこの社会課題を解決するために就職支援事業を始めました。
支援の核となる考え方はシンプルです。就職という人生の大きな決断をするにあたって、最も大事なこと。それは「いかに自分を知るか」です。
私の支援のメインは自己分析です。この自己分析を徹底的に行うことで、エントリーシートの作成や面接対策にも自然につながっていきます。
支援の根幹には心響学という学問があります。これは本来の自分、本当の自分を思い出すための学問です。生徒さんの過去の失敗やネガティブな経験、いわゆる「黒歴史」を、私と一緒に丁寧に深掘りしていきます。そして「それがあったからこそ今がある」と自信を持って言えるように、捉え方を変えていきます。オセロの黒を白に変えていくようなイメージです。
この支援を通じて、ネガティブだった自分がポジティブに変わります。面接が怖いものではなく、「私のことを何でも聞いて」と思えるほど楽しみなものに変わるのです。
一般的な就活マニュアルや面接対策講座のように、「正解」を教え込むやり方は採用していません。表面的なテクニックやマニュアルではなく、生徒さん自身の思いを自分の言葉で伝えることを重視しています。面接の際は「本当のこと」を話すように伝えています。言葉に籠る力の変化は必ず相手に伝わるからです。
自己分析は約120項目の質問から始まります。長所、短所、尊敬する人、感動した出来事など。一旦回答してもらい、それを深く掘り下げていきます。この「深掘り」には時間がかかります。1時間に1問しか進まないこともあります。
しかし、この時間は決して無駄ではありません。表面をなぞるだけの自己分析では、本当の自分には辿り着けません。時間をかけて自分と向き合うことで、初めて「これが自分だ」と確信を持って言えるようになります。
本質的なマッチングがもたらす成果
その結果として、私が支援した生徒さんの第一志望の内定率は100%です。例えば、最初にCA(客室乗務員)になれる確率を20%と自己評価していた学生が、最終的に夢を叶えた事例もあります。
ただし、この「第一志望」には少し補足が必要です。私は「ご縁があった会社が、自分にとって一番いい会社」であり、入社したところが第一志望だと捉えています。本当の自分を知り、本当の自分で臨んだ就活の結果は、必ずその人にとって最善なのです。
では離職率はどうでしょうか。
私が支援した新卒生の3年以内離職率は5%に止まります。その5%も、コロナを原因としたやむを得ない離職でした。
一般的な離職率が30%である中で、5%という数字が意味するもの。それは本人と企業のマッチング精度の高さです。
テクニックではなく本質で選んだ結果です。自分が何者であるかを深く理解し、本当の自分を企業に伝えました。企業もまた、その人の本質を見て採用を決めました。だからこそ、入社後のミスマッチが極めて少ないのです。
私の支援を受けた生徒さんからは、就活を超えた価値について語られることが多くあります。「就活支援は就活に留まらず、自分の人生を考える土台ができた」「本当の自分が見つかった」「何かに迷ったときに帰れる指針ができた」といった声です。
こうした言葉が象徴するように、自分と向き合った時間は、その後の人生においても意味を持ち続けているのです。
個人と企業、そして社会のために
30年間変わらない3割という離職率を変えるために必要なこと。それは就活テクニックから自己理解への転換です。
「どう見られるか」ではなく「自分は何者か」。この問いに真摯に向き合う就活が、企業と個人双方の幸せにつながります。
企業は、表面を取り繕った就活生ではなく、本当の姿を見せてくれる就活生と出会えます。就活生は、自分を偽らなくてもいい職場を見つけられます。ミスマッチが減れば、採用コストの無駄も減ります。新入社員は自分に合った環境で能力を発揮でき、企業は本当に必要な人材を得られます。
これは個人のキャリア形成にとっても、企業の持続的成長にとっても、そして社会全体にとっても利益となります。
一人あたり50万円以上の採用費用が無駄になり続けるという社会課題。その解決の鍵は、意外にもシンプルなところにあります。
本来の自分を知ること。本当のことを伝えること。
30年間固定化された3割という数字を変えるために、今必要なのは、就活の在り方そのものを見直す勇気なのかもしれません。
当クラブでは、社会をより良くする視点や気づきを提供する記事のご寄稿を募集しております。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。