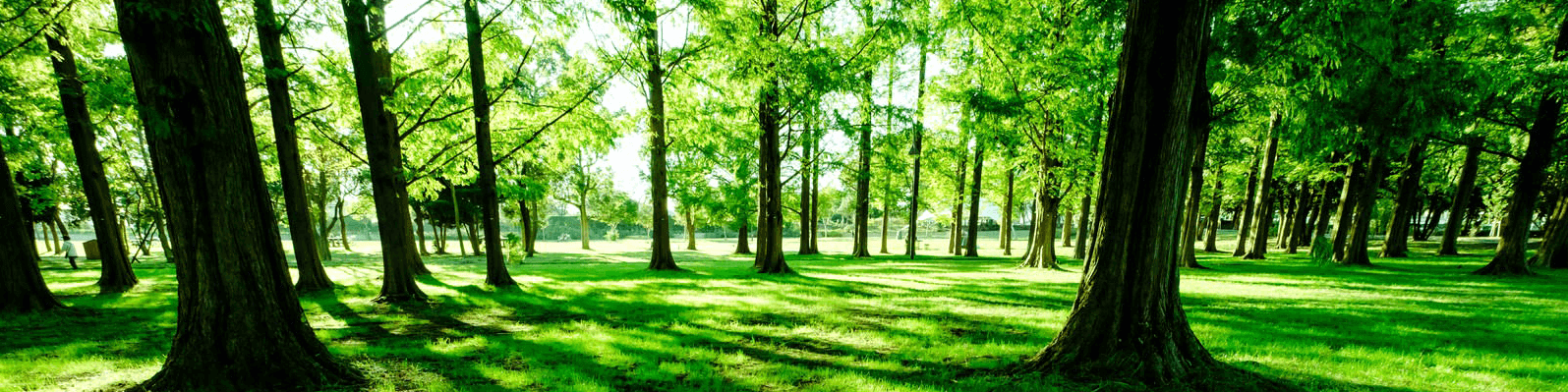市場から見放された「足」を救う 2,400万足のロングセラー
香川県に本社を置く徳武産業が展開するケアシューズ「あゆみ」は、高齢者や障がい者の歩行を支える靴として、累計販売数2,440万足(2024年8月時点)を超えるヒット商品に成長しています。現在では1日約5,000足を出荷するまでに至りました。
この靴の最大の特徴は、業界の常識では考えられない「片方販売」や「左右サイズ違い販売」に対応している点にあります。足のむくみや麻痺、装具の使用など、一人ひとり異なる足の状態に合わせてベルトの長さを調整するなど、個別の悩みに徹底的に応える姿勢が、市場における圧倒的な支持を獲得しています。出荷される靴のうち、特注対応(パーツオーダー)は全体の25%に上ります。
下請けの悲哀と「社員を守る」覚悟
現在の成功の裏には、倒産寸前の危機がありました。
徳武産業はかつて手袋縫製の下請け(OEM)工場でした。1984年、37歳で社長に就任した十河孝男氏(現会長)は、就任直後に大口取引先から「海外工場建設のため、4年後に注文をゼロにする」と通告を受けます。売上の90%を失う事態に直面したのです。
海外製品との価格競争や親会社の都合に翻弄される中、金融機関からは「会社を畳めば借金は残らない」と清算を勧められました。しかし十河氏は、社員とその家族の生活を守るため、この提案を拒否します。「どんな仕事でもいいから事業を継続する」と決断し、反対を押し切って自社商品の開発へと舵を切りました。
「売れない靴」が教えてくれた潜在ニーズ
再起をかけて参入したのは、ルームシューズ(スリッパ)事業でした。しかし、ここでも安価な輸入品との価格競争に巻き込まれ、再び苦境に立たされます。
打開策を求めて高齢者施設への訪問を重ねる中で、十河氏は「既存の靴が履けない」という切実な声に出会います。1995年、満を持して「あゆみシューズ」を発売しましたが、当初は全く売れませんでした。
失敗の原因は、一般的な靴と同様に両足セットで販売していたことにありました。老人ホームのスタッフから「高齢者はむくみや麻痺で左右の足の大きさが違うことが多い」と指摘を受け、セット販売では顧客の役に立っていないことに気づいたのです。右足だけ、左足だけ、あるいは左右でサイズが違う靴を必要とする人々がいるという、ニッチながらも切実なニーズが存在していました。
「業界の非常識」への挑戦 経済合理性よりも「困っている人」を優先
「左右サイズ違い販売」や「片方販売」は、在庫管理や製造工程が複雑になるため、靴業界では「絶対に採算が合わない」とされるタブーでした。業界関係者からは「在庫管理が大変でビジネスにならない」「素人の発想だ」と猛反対されます。
しかし十河氏は、「困っている少数の人の役に立つことこそが我々の使命であり、大手がやらない隙間産業だ」と確信し、反対を押し切って実行に移しました。一見「非効率」に見えるこのシステムが、結果として他社が追随できない独自の市場を築くことになります。競合他社が参入をためらう領域で、同社は唯一無二のポジションを確立したのです。
「社員の幸福」が「究極の顧客満足」を生む
徳武産業の強みは、システムだけではありません。商品には「お気づきの点があれば」というハガキが同封されており、顧客から年間多数の感謝の声が届きます。
ある障がいを持つ少年からは「僕の靴を作ってくれてありがとう」という手紙が届きました。再び歩けるようになった高齢者からは喜びの声が寄せられます。「歩けるようになった」という顧客の喜びを全社員で共有することで、自分の仕事への誇りと責任感が生まれています。これらの声は、社員にとって「心のボーナス」となっているのです。
十河会長は「社員一人ひとりの成長を支える経営」を掲げています。「会社は社員の幸せのためにある」という経営哲学が、結果として顧客への丁寧な対応につながっています。社員が幸せであって初めて、顧客の悩みに優しく寄り添うことができるという考え方です。
本物のイノベーションは「弱者の視点」から生まれる
徳武産業の事例は、効率化や規模の拡大だけが経営の正解ではないことを示しています。
かつての下請け工場は、今や「あゆみシューズ」というブランドを確立し、24時間365日顧客の相談に乗る体制を整えています。一見「非効率」に見える取り組みでも、顧客の深い悩みに寄り添うことで、価格競争に巻き込まれない唯一無二の価値が生まれます。
「心に寄り添う」という一見感情的なアプローチが、実は最も強固な顧客基盤と社員の結束を生み出し、企業の持続的な成長を支えています。SDGsやインクルージョンが重視される現代において、同社の「寄り添い経営」は、未来のビジネスモデルのスタンダードになり得るのではないでしょうか。