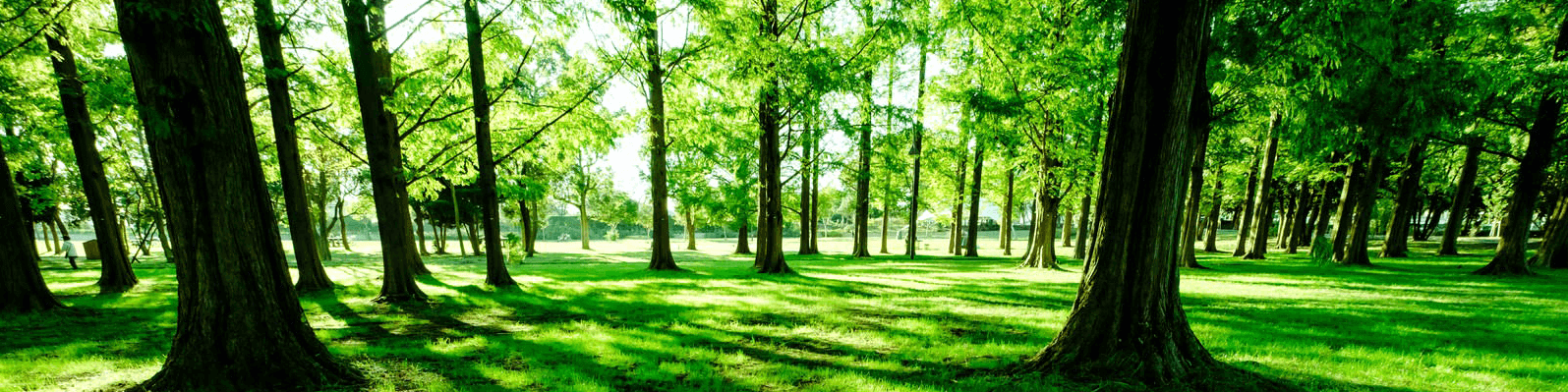岡山きずの訪問診療所の安積昌吾院長に寄稿いただきました。
ニュースが伝えない「赤字」の違和感
「病院が赤字だ」「経営が立ちゆかなくなった」。こうしたニュースを目にする機会が増えました。報道では、その原因として電気代や資材費の高騰、人件費の上昇、そしてコロナ補助金の終了などが指摘されています。確かにこれらはいずれも事実です。コロナ禍の補助金によって延命していた経営難が、補助金終了とともに表面化した側面もあるでしょう。
しかし、こうした理由だけでは説明がつかないデータがあります。それは「病床利用率の低下」です。物価が上がったからといって、それだけで病院のベッドが空くわけではありません。1990年代後半には8割を超えていた病床利用率は、直近では7割程度にまで低下しています。なぜベッドが埋まらないのか。この問いの先に、病院赤字の本質的な原因が見えてきます。
消える「急性期患者」と病床のミスマッチ
「高齢化が進めば入院患者も増えるはずだ」と多くの方が考えるかもしれません。しかし実態はその逆です。現役世代の人口減少に伴い、急性期病院の主な収益源である手術や救急(盲腸、骨折など)の需要はむしろ減少しています。一方、高齢者の増加により、慢性疾患やリハビリといった回復期の医療需要は増大しています。
この結果、日本の医療体制には深刻なミスマッチが生じています。急性期病床は約12万床が過剰となり、受け皿となるべき回復期病床は約17万床が不足しているのです。国はこの構造変化を20年以上前から予測しており、「地域医療構想」を通じて病床の機能転換を進めようとしてきました。しかし、この転換は一筋縄ではいきません。国が思い描くシナリオと、現場の病院経営との間には大きな溝があります。
「アメとムチ」による、国の病院への兵糧攻め
なぜ溝が生まれるのか。その根本には、日本の医療体制の構造的な事情があります。日本の病院の約7割は民間経営であり、公的病院も独立行政法人化されています。国が「ベッドを減らせ」と直接命じることはできないのです。一方の病院側も、地域の雇用を支える立場にあり、たとえ経営が苦しくても安易に病床を縮小するわけにはいきません。
そこで国が活用しているのが「診療報酬(公定価格)」による間接的な誘導です。その手法は大きく二つに分けられます。
一つは「ムチ」、すなわち締め付けです。2018年頃から急性期病床の重症度要件が段階的に厳格化され、軽症患者の割合が多い病院は高い診療報酬を得られない仕組みが作られました。基準を満たせなければ減収に直結するため、実質的に急性期病院の経営を圧迫する効果があります。
もう一つは「アメ」、つまり誘導策です。「地域包括ケア病棟」など回復期機能への転換を行えば収益が上がるような点数設計がなされています。さらに、病床を削減・廃棄した場合には1床あたり数百万円の補助金が支給される制度も設けられています。
加えて、過去30年近くにわたり、診療報酬全体の改定率が物価上昇率を下回り続けている点も見逃せません。これにより病院経営は慢性的に厳しい状態に置かれ、変革せざるを得ない状況、いわば「兵糧攻め」が意図的に作り出されています。
病院が動けない合理的な理由
これほどの圧力をかけてもなお、急性期病床の転換は国の想定通りには進んでいません。雇用を守る責任に加えて、病院側が踏み切れない理由はほかにもあります。
まず、「残存者利益」への期待です。国の圧力によって周囲の病院が次々と病床を減らしていけば、耐え抜いた自院に患者が集中し、稼働率が回復する可能性があります。つまり、今は赤字でもギリギリまで「急性期」の看板を下ろさないという我慢比べの構図が生まれているのです。いわば「囚人のジレンマ」のような状況であり、個々の病院が合理的に行動した結果、全体としては誰も動けないという膠着状態に陥っています。
もう一つは、政策変更への根深い不信感です。過去に国が「院外処方」を推進した際、利益誘導で調剤薬局を大量に増やしたのち、報酬を大幅に引き下げて経営を悪化させた前例があります。いわゆる「はしご外し」です。この経験があるため、今回も国の誘導に乗って病床転換を行った後で条件が改悪されるリスクを多くの病院が警戒しており、結果として転換への動きが鈍くなっています。
「箱物」から「在宅」へ変わる医療の主戦場
こうして病院側が身動きの取れない状況に陥る一方で、国の視線はすでに「病床の転換」のさらに先を見据えています。そもそも、病院という「箱物」に依存する医療体制そのものに限界があるのではないか。その問題意識が、在宅医療への大きなシフトを後押ししています。
病院建設には数十億円から数百億円規模の投資が必要であり、その回収には30年以上かかります。しかし、その間に人口動態や医療需要は大きく変化します。一度建てた「箱物」としての病院は簡単に閉鎖できず、人口減少社会においては大きな経営リスクとなります。
これに対して、国が現在強力に推し進めている「在宅医療」は、大規模な建物を必要としません。需要の変動に応じてスタッフの増減で柔軟に対応でき、経済合理性の高いシステムです。実際、国は診療報酬において在宅医療の単価を外来診療の数倍に設定するなど、明確な利益誘導を行っています。医療の主戦場を「箱物」から「在宅」へとシフトさせる意図は明らかです。
医療の質をどう守るか
病院経営の悪化は、「病床削減と在宅シフト」という国が描く巨大なシナリオの中で起きている構造的な現象です。物価高や補助金の終了は、あくまでその表層にすぎません。
しかし、受け皿として期待される在宅医療の現場にも課題があります。在宅医療の担い手は内科医が中心であり、床ずれや傷の処置に対応できる形成外科医などの専門医が不足しています。病院の病床が減る一方で、在宅では対応しきれない「医療の空白」が生まれつつあるのです。
制度の転換が進む中で、患者が適切な医療を受けられなくなるリスクをどう防ぐか。仕組みの成熟が今、強く求められています。
当クラブでは、社会をより良くする視点や気づきを提供する記事のご寄稿を募集しております。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。