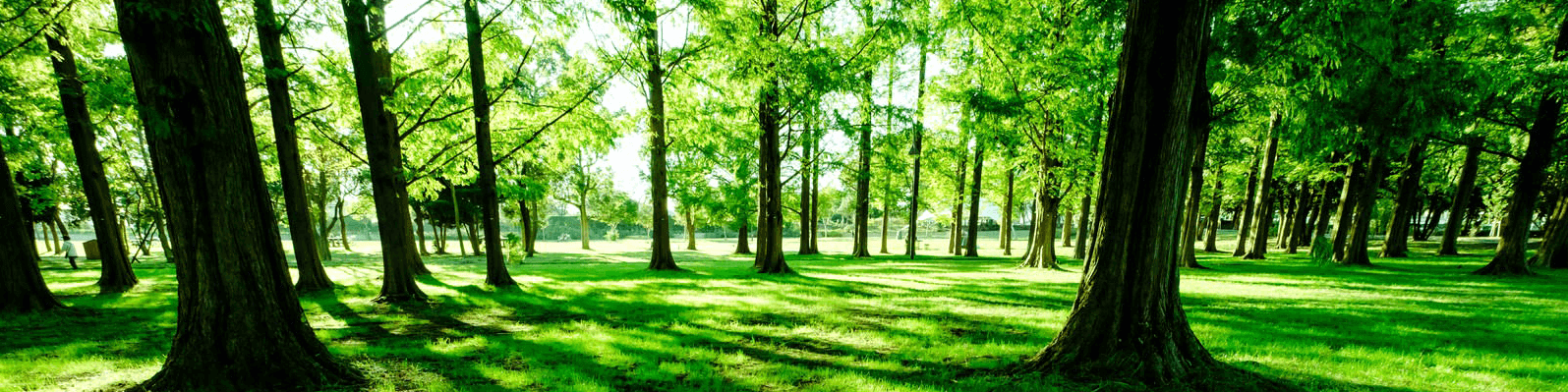岡山きずの訪問診療所の安積昌吾院長に寄稿いただきました。
在宅医療の現場は「内科医」の世界
国は現在、病院という巨大な設備投資(箱物)のリスクを避けるため、診療報酬に経済的インセンティブを組み込み、在宅医療への移行を強力に推し進めています。その結果、訪問診療の件数は急増しました。しかし、その担い手のほとんどは内科医です。高血圧、糖尿病、慢性心不全といった全身疾患の管理や投薬指導は行われているものの、外科的な処置が必要な場面では「対応できる医師がいない」という問題が発生しています。では、実際の在宅の現場ではどのようなトラブルが起きているのでしょうか。
家庭内で起きる「外科的トラブル」に医師がいない
内科医の守備範囲を超える問題は、決して特殊なケースではありません。在宅療養中の患者さんにとって、生活の中でのケガや身体トラブルは日常と隣り合わせです。転倒による傷、火傷、寝たきりに伴う褥瘡(床ずれ)は頻繁に起こります。さらに、糖尿病が進行して足が壊死していく「糖尿病性足壊疽」や、病院での手術後の傷の経過観察が必要になるケースもあります。
大きな病院に入院していれば、内科の主治医が患者の床ずれに気づいた時点で、院内の皮膚科や形成外科の医師にすぐ診察を依頼(対診)できます。ところが在宅医療では、一人の患者を診ている主治医が、他の科の専門医に気軽に相談したり、診察を依頼したりする仕組みがまだ確立されていません。本来なら治せるはずの傷が適切な観察や処置を受けられないまま悪化してしまう。こうした「医療の空白」が、在宅医療の現場に生まれているのです。
「家にいたい」という願いが叶わなくなる時
多くの患者さんは「最期まで自宅で過ごしたい」と願っています。しかし、たとえば糖尿病性足壊疽が悪化し、激しい痛みを伴うようになると、専門的な処置ができない内科医だけでは在宅での管理が困難になります。本人は家にいたいのに、適切な処置を受けるためにやむなく病院へ搬送され、そのまま入院先で最期を迎えることになってしまう。こうしたケースは決して珍しくありません。
もし専門医が早期に介入し、傷の重症化を防ぐことができれば、入院せずに住み慣れた家での生活を続けられる可能性があります。在宅医療における専門医の不在は、患者さんの暮らしの選択肢そのものを奪いかねない問題なのです。
せっかくの「併診制度」が使われない理由
国もこの問題を認識し始めています。2018年の診療報酬改定では、主治医(内科医など)の依頼を受けて専門医(形成外科医など)が訪問診療を行う「併診」の仕組みが整備されました。
しかし、この制度は十分に活用されていないのが現状です。まず、こうした連携が可能であること自体を知らない内科医やケアマネージャーが多数存在します。また、制度上、専門医の訪問は原則「月1回」などの回数制限が設けられており、週に数回の処置や観察が必要な傷の管理には実態としてそぐわない側面があります。制度はあっても、現場のニーズと合致しておらず、連携の型もまだできていないのです。
専門医連携が切り開く在宅医療の次のフェーズ
かつて20年前には珍しかった訪問診療が、今では医療の柱の一つになりました。これからは、在宅医療の中に「専門医」が入っていく新しいフェーズが求められています。
内科医が全身管理を担いつつ、形成外科医のような専門家が傷や床ずれの管理をサポートする。こうした併診による連携は、入院を回避し、患者さんのQOL(生活の質)を守るうえで欠かせない取り組みです。制度の未熟さという壁はありますが、この連携を広げていくことが、在宅医療を本当の意味で成熟させる道ではないでしょうか。
当クラブでは、社会をより良くする視点や気づきを提供する記事のご寄稿を募集しております。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。